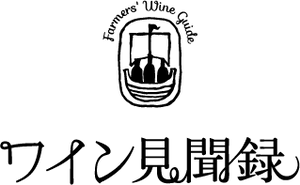ラ・ライア
ガヴィ本来の個性をビオディナミで再生
180haの土地で有機野菜、古代小麦栽培、ファッソーネ牛の放牧をしながらワイン造り
デメテルの基準を遥かに下回る少ない酸化防止剤添加でピュア、クリーンな味わい
❖畑の周囲の環境が大切❖
大手ボトラーによってスーパーマーケットの安ワインになってしまったガヴィ。もはや忘れ去られた産地でしたが、2003年ジョルジョ・ロッシ・カルロが立ち上がります。
『ノヴィ・リグレ地区の180haのも及ぶ荘園と森を購入し、ファッソーネ牛の放牧、栗、有機野菜の栽培。そして有機栽培で高品質ガヴィの復活を目指す』
180haの所有地は葡萄畑、野菜畑、牧草地だけでなく、沢山の種類の野生動物が自由に過ごせる栗、アカシア、ニワトコの森と湖を含んでいます。
『歴史的なガヴィの丘陵部に45haの葡萄畑を再生し、周辺に葡萄以外の野菜栽培。牛の放牧。そして自然の森を残し、自然な生態系の中での葡萄栽培に意味がある』
2007年にはイタリアで最も厳しい有機認証団体デメテルの認証も取得。全キュヴェはデメテルの基準に合った有機栽培で栽培された葡萄のみとなっています。
『何世紀もの間、コルテーゼという土着品種が育ってきたのに、工業的ワイン造りで本来の個性を失ってしまう。この土地の本当の個性を再生するのがラ・ライアの目的』
2005年にはカンティーナ脇に小さな学校も開業。ガヴィの自然を活かした農業を、未来に継承していく為、ビオディナミの提唱者シュタイナーの教えを広めています。
『ガヴィの個性を再生し、残していく為には葡萄畑だけでなく、生物多様性の実現と、それを実践し学ぶ場所が必要。本当のガヴィを絶やさない為の学校』
ビオディナミでのワインの生産、有機野菜の栽培、流通、ピエモンテの固有種ファッソーネ牛の放牧。更にシュタイナー学校の創設というジョルジョ・ロッシの壮大な夢の実現でした。最初に着手したのは敷地内での一切の化学薬品の使用禁止。今ではミツバチ、受粉昆虫、そして様々な種の動物が戻り、生物多様性のオアシスとなっています。
『敷地内ではビオディナミ調剤、自家製のコンポスト、緑肥、最低限の銅と硫黄しか使わない。20年以上続けているので土壌は活性化し、本来のエネルギーを取り戻している』
スペルト小麦やライ麦など、この地域の古代作物を植えることで土地の生命力が正常化し、ファッソーネ牛を含む家畜の放牧が再開されました。
『カンティーナの壁はピセというこの地域伝統の土壁を採用。荘園内の年粘土に小石、干し草を混ぜ込み木製の骨組みに塗り付けていったもので、これもこの土地ならではの文化』
❖低温で香を確保❖
『コルテーゼは繊細な品種なので丁寧に扱わないと鮮烈な香を失い、酸化も引き起こす。扱いが難しいので、正しく醸造されないと平坦な味わいになりがち』
大量生産ではコルテーゼの繊細な香やナッティな風味は失われ、平坦な味わいになってしまう。大手ボトラーの出現でガヴィの名声は完全に地に落ちてしまったのです。
『機械収穫では、葡萄果は少し破砕してしまい、モストが酸化してしまい、本来の繊細さは失われてしまう。コルテーゼ種は手作業でしか本来の個性を表現できない』
収穫は気温の低い早朝に行い、果汁の温度が低い状態で収穫。すぐに低温の部屋に入れて低温をキープしながら1晩置き、ステンレスタンクで低温から醗酵を開始します。
『低温で発酵を開始させる事で揮発的な果汁由来の香を抽出する。15度から醗酵を開始し、28度以下の範囲で行う事がガヴィにとっては非常に重要』
ヴィンテージによって数時間の短いマセラシオンをする事でコルテーゼ種の果皮に含まれる要素もワインに移していきます。少しの時間だけなので繊細さを失いません。醗酵終了後、シュール・リー熟成。長すぎる澱との接触は品種個性を消してしまうので3ヶ月のみ。ボトリングは窒素を使い、一切酸素と触れ合わずに行われます。
『酸化防止剤の添加量は、イタリアで最も厳しいデメテルの基準の1/3以下でかなり少なくなっている。これはワインを常に低温で管理し、バクテリアの活動を抑制する事で可能となる』
❖希少なガヴィ・リゼルヴァ❖
平均植樹率は4,500本/haで、ベースのガヴィでも平均樹齢は15年以上。最も古い樹は70年を超します。一般的な造り手より、かなり高い樹齢になっています。
『最も樹齢の高い70年の区画、ラ・マドンニーナのコルテーゼは葡萄のポテンシャルが高いので、通常より長く熟成させたガヴィ・リゼルヴァが造られる』
ガヴィでリゼルヴァを造っている造り手は3軒程度しか残っていません。樽に入れては品種個性がマスクされてしまうので6ヶ月ステンレスタンクで熟成後、6ヶ月瓶内熟成。
『収量が少ない高樹齢のコルテーゼは、長く熟成させる事で樽熟成のようなナッツやバターのようなクリスピーで香ばしい味わいが出るのが面白い』
単一畑のガヴィ・ピセはカシネッタ畑の葡萄のみで造られます。この畑は特に酸化鉄を多く含む赤土にローム質の砂質が含まれるので、ガヴィらしい個性的な味わいを表現します。
『ピセはとても個性的なので1年以上の長いシュール・リー熟成を採用。2018ヴィンテージからはオーストリアのストッキンガー製の大樽で熟成させている』
ソアヴェ、オルヴィエート。そして、ガヴィも元々持っているポテンシャルが高いから古くから葡萄が栽培されてきたはず。本来の個性を再生するのは、イタリアワインにとって重要な事なのです。