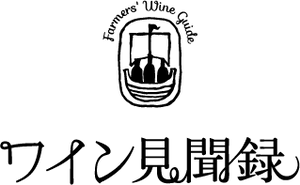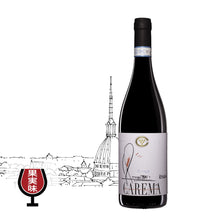| 生産地 | イタリア / ピエモンテ |
|---|---|
| 品種 | ネッビオーロ |
| ヴィンテージ | 2017 |
| 種類 | 赤 |
| 醸造・熟成 | 2009年まで木樽30ヶ月後瓶内12ヶ月以上熟成が義務だったが2010年からは36ヶ月の木樽熟成のみとなった。大きなセメントタンクでゆっくりと発酵させることで要素の多いワインに仕上がる。 |
| アルコール度数 | 13% |
| 容量 | 750ml |

熟成ネッビオーロの複雑だ味わい
オレンジ色を帯びたガーネット。ドライフラワーやオレンジの皮、シナモン、甘草、ココアの香り等々の豊富な香。口の中は非常に柔らかく、甘みのあるタンニンと繊細なタンニンの余韻が心地よい。
こんなワインです
その年の状態の良い葡萄のみを選別して使用。段々畑で棚仕立という畑で栽培されたネッビオーロ。収穫後、大きな冷蔵庫で 1 晩冷やしてから大型セ メントタンクで醗酵。20 日間程度のマセラシオン。醗酵初期は優しくルモンタージュを行う。熟成は栗の木樽とスラヴォニア大樽を併用して 18 ヶ月間。そ の後、瓶熟成 18 ヶ月を経て出荷。野性味があり、旨味も強いのでジビエ料理にも相性が良い。
プロデュットリ・ネッビオーロ・ディ・カレーマのワイン
WINERY
生産者情報

プロデュットリ・ネッビオーロ・ディ・カレーマ

石柱と石壁が育てた最北のネッビオーロ
段々畑の棚仕立というネッビオーロ栽培としてはあまりにも特殊な産地
ここにしかない独特の個性はイタリアが忘れかけている地酒の素晴らしさを教えてくれます
❖ピエモンテ最初のDOC❖
トリノからアオスタに向かう途中、ピエモンテ最後の村がカレーマです。ドーラ・バルテア川に沿った狭い平野部に僅か700人の村人が住み、背後には急斜面のアルプス山脈が迫ります。
『フランスからワイン文化が伝わり、早い時期にワイン造りが始まった。高貴なワインとして知られ、ピエモンテで初めてDOCを獲得したのもカレーマだった』
カレーマは過疎化が進み、住人の高齢化が問題になっています。耕作放棄される葡萄畑が増え、現在、17haまで葡萄畑は減ってしまっています。
『プロデュットリ・ネッビオーロ・ディ・カレーマは1960年にカレーマのワイン文化を後世に残すことを目的に設立された組合。組合員は全員、他の仕事と兼業している』
カレーマの生産量のほとんどが、この組合によるもの。今も101名の村人が所属して71の畑を所有。共同で畑を管理し、醸造、販売まで行っています。
『組合員の平均年齢は55歳と高齢なので段々畑では働けない。皆、個人ではワインを造る事ができないので共同で助け合い畑や文化を守っている』
現在の社長は郵便局員との兼業。醸造責任者はカレーマ出身でピエモンテワインのスペシャリスト。ボトリングやエチケット貼りはお年寄りが担当。
『1960年から1983年までは各栽培農家の自宅で収穫、発酵までを行っていた。発酵終了後、カンティーナに持ち込みアッサンブラージュし、樽熟成を行っていた』
1960年に設立、1965年に今の場所に移転し、徐々に醸造設備を拡充。1984年からは収穫から醗酵、熟成、瓶詰めまでカンティーナで行うように。
『カレーマの文化を残す為の組合で、お年寄りでも働けるようにする事が目的なので、生産量は変わらず、ワインのスタイルも昔のまま変わっていない』
新しい醸造技術も商業的思想も入ってこない田舎の協同組合。お爺ちゃん達が楽しく働いています。だからこそ、昔からの栽培や仕立、ワイン造りが残されているのです。
❖伝統的石柱ドゥピン❖
カレーマはネッビオーロが育つ限界地点と言われます。この冷涼な土地で葡萄栽培を可能にしているのが「ドゥピン」と呼ばれる独特な畑の作り方。
『石柱と石壁で作られた段々畑。地中の岩を掘り出して作られる。この石が日中に温められ、夜間に熱を開放し、葡萄樹を暖めるので北の産地でも成熟できる』
この石柱がドゥピンと呼ばれるこの地方独特の工夫。急斜面に積まれた石段は効率が悪く、危険だが、カレーマでは、このシステムでないとネッビオーロは熟す事ができません。
段々畑にはトラクターは入れません。植樹から剪定、草刈り、収穫まで全てを手作業で行うしかありません。収穫は30kgのカゴを背負って上り下りするので非常に危険。
『仕立ては棚仕立。積雪量が多いので雪で葡萄樹が埋もれて死なないように高く仕立てる必要がある。また、雨が降っても風通しが良いので病気を防ぐ事ができる』
ドゥピンと石壁による段々畑と棚仕立による葡萄栽培でないとカレーマでのワイン造りは成立しないのです。先人達の知恵で出来上がった独特のワイン文化です。
『ランゲのような力強さや偉大さはカレーマにはない。必要ない。ピエモンテ人も忘れてしまったかもしれない地酒としてのネッビオーロの素晴らしさが残っている』
❖栗の木樽❖
『2013年、カンティーナは修復され、あまりに古い樽を捨て、スラヴォニア大樽に置き換えました。一部はいまだに栗の木を使った大樽があり、併用しています』
発酵は大型のセメントタンクがいまだに使われています。開放式の古い大きな発酵槽では醗酵がゆっくり進みます。色々な種類の酵母が活動できるのでワインは複雑味を得るのです。
『栗の木樽はカレーマにとって重要。硬く酸素を通し難く、少しのタンニンを与えてくれる。カレーマでは60年代から栗の木樽での熟成が行われてきた』
カレーマの土壌は花崗岩。石英、長石、黒雲母とミネラルが豊富な鉱物が多いのが特徴。穏やかで繊細な酸味と厳し過ぎない骨格のネッビオーロを育ててくれます。
『花崗岩、棚仕立のネッビオーロは柔らかで温和ですが、実は酸度は高く、ミネラル感も強い。栗の木樽のタンニンと大樽での熟成と非常に相性が良い』
カレーマは12か月間大樽熟成後、12ヶ月瓶熟成。カレーマ・リゼルヴァは18ヶ月間大樽で熟成後、18ヶ月間瓶熟成。リゼルヴァは野性味を持ち旨味も強いもの。
『他のどの産地のネッビオーロとも似ていない唯一の個性である「カレーマは葡萄畑、セラーだけでなくカレーマの人が造り上げた組合による文化なのです』
過疎化と高齢化で存続の危機にあるプロデュットリ・ネッビオーロ・ディ・カレーマ。カレーマの人達の温かさや歴史を感じさせてくれる貴重なワインです。